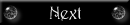『マスクドライダーシステム?』
ステラと同じ境遇―――元B.C.F.メンバーであると名乗り、てれび戦士と接触した天道総司と日下部ひより。
二人はリーフのメインブリッジにて、出動待機が告げられているてれび戦士たちを集め、B.C.F.の計画の一端を告白した。
「B.C.F.がそのような計画をしていたと?」
「でも、その“ライダーシステム”って、何なんです?」
レッドの質疑に対し、天道が要約を説明し始めた。
ライダーシステムは、今から25年以上も前から計画されていた、白兵戦特化型特殊機構計画として、組織の上層部で極秘裏に進められていたものだ。
“コア・インゼクター”と呼ばれる昆虫型コアメカを、ベルトやブレスなどのアイテムに装着することで、“ヒヒイロカネ”と呼ばれる未知のレアメタルで造られたアーマーと、強化型ライダースーツを同時に装着することが出来る。
ライダースーツを身に纏ったときのスペック(能力)は、並みの人間の身体能力の域を遥かに超える。
それをうまく活用し、実戦に投入すれば、一人だけでナチュラルの軍隊1個師団と渡り合えるほどの能力が身に付くだろうと推測されているんだ。
生身の状態でライダーに立ち向かおうとでも考えていると、致命傷は避けられない。
「マユとアリシアの大怪我が、それを物語ってるわね…。」
彼らが訪ねて来たとき、マユとアリシアが大怪我を負っているのを、杏奈は目撃している。
あれがライダーシステムを目の当たりにしたものの末路と考えると、背筋が凍る……。
また、余談だが、二人が運ばれてきた際、ラクスに酷似した少女・ミーアも同時に運ばれてきたために、てれび戦士は彼女の傷の手当ても行うことになっていた。
「ちょ、ちょっと待て!」
ここでゴルゴが制止をかけた。
「そのゼクターってヤツがもし大量生産されていたとしたら、それこそ最強の部隊が完成するじゃないか!」
「ところが、そう簡単にはうまくいかないんだ。」
天道が冷静にゴルゴの言葉を否定した。
それを引き継ぎ、ひよりが説明する。
ライダーシステムは、B.C.F.のメンバー内部での、極僅かな人間しか装着が許されないんだ。
それを証拠に、ゼクターにはそれぞれ人工知能を備えていて、自分が主と認めた人だけに付き従うことになっている。
つまり、人間がゼクターを選ぶんじゃなくて、ゼクターが主を決めるんだ。
「ふむ……、“真の武具は持ち主を選ぶ”とは、よく言うものだ。」
感慨深く有沙女王が呟く。
まるで、GUNDAMとシードクリスタルの関係を表しているかのようだ。
「ふぅ…やれやれ……」
「やっと一段落着いたよ……。」
一仕事を終えたというような顔で、レイシー兄弟がブリッジに上がってきた。
「おぉ、ドクターレイシー、チアキ。どうじゃ、二人の容態は?」
「予想以上に傷がひどかったですけれども、命に別状はないですね。数日ほど休めば傷も塞がるかと。」
どうやら一命は取り留めたようだ。
てれび戦士も、そして人一倍彼女らを気遣っていたプレシアとリニスも、安堵した。
「ところで、女王さま、話題を変えますけれども……例の暗号は、どうなりましたか?」
「ん?…あぁ、あれか?」
ゴルゴの切り出した話題に、有沙女王も気付き、彼女は懐から“あの紙”を取り出した。
「大体は解けてきておるのじゃが、これ以上はわらわにも……。」
「そうですか…、おいレッド、そっちはどうだ?」
「合間を縫ってやっとるんだが、全然わからへんねん……。」
状況が飲み込めない天道とひよりは、徐に訊ねた。
「おい、その暗号と言うのは、何の話だ?」
「よかったら、ボクらも手伝うけど…。」
それを聞き、ドクターレイシーが早速動いた。
「でしたら、ぜひとも!これがその暗号です。」
二人がレイシーから一枚の紙を受け取る。
「…ほぉ…、クロスワード形式の暗号か……、随分とユニークだな。」
天道がその紙をぼんやりと眺めている隣で、ひよりはいつになく真剣に暗号と向き合っていた。
「…?…ひより…?」
異変に気付いた天道が声をかけるが、ひよりはそれに気付かない。
それほどに真剣だった。
すると、徐にクロスワードのマスに指を当て、ゆっくりと滑らせていった。
「女王さま、これはちょっと表記が違うんじゃないですか?」
「え?そうか?」
てれび戦士が暗号解読にもたついている間にも、ひよりは問題とマス目とを交互に見合わせて、時折指を滑らせていく。
滑らせた後には、アルファベットで綴った言葉が刻まれていった。
「卓也さん、それ文字数が違うと思いますよ?」
「あれ?こっちだったっけ?」
そして、それを繰り返すこと、わずか6分足らず。
「出来た。」
『………………え?』
1週間以上悩んでいたてれび戦士が、全員驚きの表情でひよりを見た。
彼女の隣には、苦笑いの表情を浮かべる天道が。
「てれび戦士、どうやらたった今、ひよりが暗号を完璧に解いちまったようだ。」
そして微笑を浮かべるひよりの手には、完璧にまで埋め尽くしたクロスワードの紙があった。
『……早っ!!!!!!』
ダイダルストライカーズの全軍(オーシャンガーディアンズを除く)が、ゾロアシアへと出撃して間もない頃。
「……?」
「…あれって……?」
なのはの現状を見舞おうと思い、病棟エリアの廊下を歩いているとき、恭也と美由希の眼に一体の大型のウサギの姿が飛び込んだ。
この基地のメンバーのシゾーだ。
しかし、今日は様子がおかしい。
どうして隠れているのだろうか……?
何かあったのだろうか?
二人は気配を殺し、シゾーの傍による。
「どうした、シゾー。」
「?あ、恭也と美由希。丁度良かった。……こっそり、見てみるピョン。」
「……?」
言われるままに、こっそりと顔を覗かせると、なのはの病室の前に一人の少女の姿が立ち止まっているのが眼に見えた。
「……誰なの、あの子。」
「判らんピョン。でも少なくとも、オレの見た限りではダイダルストライカーズの関係者ではないピョン。」
シゾーでも知らない、謎の少女。
すると、その少女は扉を開けてなのはの病室へと入っていった。
「あ、なのはのところに入っちゃった!」
「調べてみる必要があるな。シゾー、ここは俺と美由希に任せてくれ!」
「よし、気をつけるピョン!」
それから二人は、なのはと謎の少女――ヴィヴィオの会話を立ち聞きし、末っ子の心の傷を受け取るや否や、恭也は心の底から溢れる怒りを我慢できず、美由希と共になのはの病室へと入り込んだのだった。
「さっきから黙ってお前の話を聞いていれば、お前はそんなにまで自分を責め続けていたのか!!??」
霊力を保有する二人であるが故、二人には精神体となった彼女の姿がよく見えていた。
“……。”
非常に気まずい雰囲気になってしまったせいで、なのはは視線を逸らして沈黙した。
しかし――――――。
「……お前の仲間のユーノたちから、お前の最近に関することは全部聞かせてもらっている!」
“―――!!!!”
「その上で言わせてもらう。この大馬鹿野郎ッ!!!!!!!!」
“!!!!!!!!!!”
心臓が飛び出るほどの一際大きな兄の怒声に、なのはは竦みあがった。
しかし、その次の怒声が来なかった。
目を開いて視線を兄に向けると、兄は肩を震わせていた。
そこまで溜め込んでて、自分を責め続けて……、友達にも話せないほどに苦しんでたなら……っ…なぜ俺たちを頼らないっ!!??
そんなに俺たちは頼りないのか!?
俺たちはお前にとっての荷物なのか!?
……そりゃ、俺たちだって、今までお前を独りにしたことは、すまなかったって思ってるさ…。
魔法の事だって俺たちは良く知らないから、不甲斐ないアドバイスしか出来ないことだってあるかも知れない……。
だけど、だからってそんなのは、幾らなんでも……悲しすぎるじゃないか!!!
なのは……お願いだから…っ…、あたしたちにも頼らせてよ…っ…!
なのはが抱えている苦しさも、悲しさも、痛みも……全部、あたしたちにも分けてよ……っ…!
あたしたち、兄妹でしょ…?
兄妹なら、それが当たり前じゃない…っ…!
あたしや恭ちゃんだって……、一緒になって…っ…、なのはを支えてあげたいんだからぁ……!!
大粒の涙の雫と共にこぼれ出た、兄と姉の告白。
美由希に至っては耐え切れず、その場で泣き崩れてしまっている。
“…おにい、ちゃん…っ…、…お、ねえちゃ、ん…っ…っ…。”
自分の記憶の中でも滅多に見たことのない兄と姉の涙と、初めて知った、自分に対する二人の思い。
それが、胸の奥で分厚く大きな氷の塊となっていた、自分の辛い思いと心の痛さを一気に溶かし、なのはの瞳から溢れる涙となって、溢れ出した。
ヴィヴィオはその状況を見届け、ここからは3人の役割だと認識し、精神アクセスを解除、自分となのはの精神体を、元の体に戻した。
瞳を閉じていたヴィヴィオは、ゆっくりとオッドアイを開き、涙を流す恭也と美由希の傍らに寄った。
「恭也さん、美由希さん。」
優しい声をかけられた二人は、視線をヴィヴィオへと向けた。
「ここからは、お任せします。」
そう言って、少女は二人をベッドの前へと促した。
二人はなのはの眠るベッドの傍らへと寄る。
程なくして、ついになのはの意識が戻った。
「…ぁ……お、にい、ちゃん…、おねえ、ちゃん……!」
焦点が合ったのか、なのはの視線は二人を移した。
同時に、なのはの目元から大粒の涙が……。
「…っ…、…あたし……あたし…っ…。」
それ以上は続かなかった。
どんな言葉を言えばいいのか、判らなかったのである。
だが、そんなことはどうでもいい。
今、自分たちに出来ること、それは―――。
―――ギュッ
こうして、幼い涙を抱える妹を、抱きしめてあげることだ。
「!!…………ぅ…うっ…、ぁ…っ、
うわああああぁぁぁぁ……!!!!」
なのはは、生まれて初めて、心の底から泣いた。
ずっと、求めていたのかもしれなかった、温かさに包まれて…………。
「…ぅ…っ………、ホントは…っ…、とても辛かった……っ、寂しかった…っ…、凄く、凄く…苦しかったよぉ…!!!うああああぁぁぁぁぁぁ……!!!」
ずっと溜め込んでいた苦しさを、懺悔するように吐き出し、なのははずっと泣き続けた。
それを見守ったヴィヴィオも、“これで、もう大丈夫”と言わんばかりの笑みを浮かべ、ゆっくりと頷いた。
ちなみに、ドアの外でもヴィヴィオと同様、その様子を見守っていた者が二人。
「…フッ……シゾーよ…“兄妹”、と言う存在も…、悪くはなさそうだな……。」
「…そうだな、ネガタロス。」
「……そう……ステラがそんなことを…。」
意識を取り戻したフレイは、アウルとスティングからステラの心の叫びを耳にした。
その彼らの両の傍らには、加賀美とライガーシールズの面々が。
あの一件の後、3人は加賀美に連れられ、G.L.B.へと出向。
加賀美もまた天道たちと同様に、B.C.F.の計画である“マスクドライダーシステム”の概要を告白したのである。
尤も、ライガーシールズたちもてれび戦士たちと同様、B.C.F.がゾロアシアに出現したと言う情報により、出撃すべきか否かの複雑な状況にあったがゆえ、現状では待機の状況にあったというのが実情なのだが……。
閑話休題。
「なぁ、フレイ。僕たち、今まで言われるがままに行動して、コーディネイターを殺してきたけど……、それって、間違ってたのかな…?」
B.C.F.らしからぬ言動を口にしたアウルに、全員が少し動揺した。
特に、今まで行動を共にしていたフレイとスティングにとっては、予想もしてなかった言葉だった。
「どうして、そんなことを!?」
すると、アウルは、まるでライガーシールズの立場に立ったかのような言葉を口にした。
さっき、ステラが言ってた言葉……“人の友達や兄弟を平気で殺す人が仲間なんて言えるのか”って……、それを言われて、僕、少し考えたんだ。
僕たちは、単純に“コーディネイターはシードピアの悪魔だ”、“平和を乱すバケモノだ”って、大人たちに言われて、それを信じて戦ってきたけど………、考え直してみれば、僕たちナチュラルだって友達や兄弟がいることがあるし、“家族”だっている可能性が少しでもあるって事だろ?
そう思えば、コーディネイターだってそう言うのがいても、不思議はないんじゃないか…?
もしも、そういう友達や兄弟のなかで、コーディネイターが一人でも居て、そいつがナチュラルと一緒にいて、とても仲が良かったとして……、いきなり“そいつを殺せ”とか“縁を切れ”とか言われたりしたら、どう思うかな……。
多分……とても辛いことになると思うんだ……。
……理解できない話ではなかった。
むしろ、物凄くしっくり来る話だ……。
「…アウルくんの考え、良く解るよ。」
率先して同意を示したのは、キラだった。
「僕はコーディネイターだけど、ナチュラルのカガリとは、双子の姉弟だ。だから、もしそんなことになったら……、僕には絶対出来ないよ…。」
「…私も同じだ。キラは、時々ムカつくところがあるが、根はいい奴だし、誰よりも全ての人間たちと触れ合いたいと言う意志が強いからな。それに…大切な弟を自分で殺すなんて事、私には無理だ…。」
実例がここにいた。
“悲劇”を生き延びた二人は、誰よりも大切な存在を失うことを恐れていたのだ。
それを、仲間であり戦友でもあるライガーシールズは、よく解っていた。
ふと、スティングが何かを思い出した。
そう言えば、ステラ、B.C.F.に入る前は義理の兄貴と義理の妹がいるって話を聞いたな…。
ステラがあんな言葉を言ったって事は、きっとあいつ、コーディネイターであれナチュラルであれ、心の底からその兄妹を愛していたんだろうな。
俺自身、その兄弟と言う存在を持ったことはなかったんだが、アウルやステラと一緒に過ごしていたうちに、それに似た思いが生まれてたのかもしれないな……。
スティングとアウル、数年間と言う短い間とはいえ、ステラと共に行動した二人は、少しずつ今までの考えを改め始めていた…。
……その沈黙を破ったのは、歌姫だった。
「スティングさん、アウルさん、フレイさん。」
3人はゆっくりとラクスに視線を向けた。
そこにいたのは、テレビを介する表舞台に出るときの、凛としたラクスの表情だった。
「あなたたちは今までB.C.F.として活動していたが故、“コーディネイターの殲滅”と言う野望と、“蒼き清浄なる世界のために”と言うテーゼを掲げて、戦ってきました……。あなたたちはこれからも、それをあなたたちの信念として、言われるがままに戦い続けるのですか?」
研ぎ澄まされた槍で貫かれるような、鋭い眼差しで自分たちを見つめるラクスに、3人は逸らすことが出来なかった。
そして、少しながらの心の迷いをさらに助長させる、彼女の言葉に、声が詰まった。
「そうであるならば、私たちライガーシールズは、再びあなたたちの敵となるかも知れません………、そして、ステラさんもまた、同じように………。」
――――――!!!!
“ステラの大事な人、傷つけた……!!!!”
“絶対に許さない!!!!!!!”
脳裏に過ったのは、心の底からこみ上げる怒りを露にした、ステラの涙。
あれが再び繰り返される可能性が大きいことを、ラクスは警告しているのだろうか……!?
「私たちはともかくとして、もし、敵だと言うのならば、あの子…ステラさんを撃ちますか?ブルーコスモス・ファミリーの、スティング・オークレー、アウル・ニーダ、そして、フレイ・アルスター。」
……言葉が出なかった………。
組織の命令なら、それに従えばそれで十分だと思ってた。
しかし、ステラの怒りと悲しみを経験した今回の一件で、3人は大きく迷うことになった。
結局、自分たちが信じてた道は、一体なんだったのだろうか………?
---to be continued---
☆あとがき
中途半端なところで区切ってしまいましたね今回は……。
それにしても、ひより、あっという間に暗号を解いて見せちゃいましたねぇ……
終盤のラクスのセリフ、明らかにSEED第1期第36話のラクスのセリフそのまんまですね(苦笑)
実は、僕がSEEDシリーズを見始めたのはその中途半端な時期からだったりして(笑)
さて、次回はいよいよ、GUNDAM最強装備の封印が解かれます!
○おまけと言う名の次回予告(第73話)
―――ピリリリリ、ピリリリリ
キラ「あ、メールだ。」
携帯電話を取り出し、メールの中身を確認する。
差出人:不明
『まもなく、GUNDAMの切り札が覚醒する。もし、使いこなせないようなことがあれば…………、
お前は圏外だ』←ドラッグ
キラ「………………なにコレ?……」